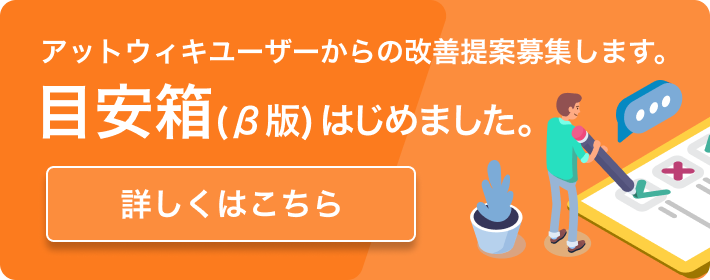「第一章 運命の足音 5」の編集履歴(バックアップ)一覧はこちら
「第一章 運命の足音 5」(2005/05/10 (火) 22:55:41) の最新版変更点
追加された行は緑色になります。
削除された行は赤色になります。
第一章 運命の足音 5
「それで・・・・・・、リキアの騎士のお二人さん。話を聞かせてもらえるんだったわね?」
二人の騎士は乗っていた馬を降り、リンの前に進むと口を開いた。
「はい。我らは、リキアのキアラン領からある方を訪ねに参りました」
「リキア・・・・・・・。西南の山を越えたところにある国ね?」
サカから出たことのないリンだが、おおよその国の位置は知っていた。
自分の知識を正しかった事を肯定するように、ケントはうなずいた。
「そうです・・・・・・。十六年前に遊牧民の青年と駆け落ちしたマデリン様の使者として」
「・・・・・・マデリン?」
「我らが主人、キアラン侯爵、ハウゼン様のたった一人のご令嬢です。ずっと消息を知れず、侯爵も、もう娘はいないものだとあきらめておられました」
「しかし、今年になって初めてマデリン様からの便りが届いたのです!『サカの草原で、親子三人、幸せに暮らしている』。その事に、侯爵はとても喜ばれ自分には『十五になる孫娘がいる。知らぬ間に、おじぃちゃんになっていたようだ』と、それは、幸せそうな顔で発表なさいました。孫につけられたという名前『リンディス』は、侯爵が、早くに亡くされた奥様方のお名前だったのです。」
「リンディス・・・・・・」
「娘夫婦の思いやりに、頑なだった心も、とかされたのでしょう。なんとか、ひと目なり娘たちに会いたいと願われ、我らがここに来たんですが・・・・・・。マデリン様は、手紙を出した直後、亡くなられていて・・・・・・、その事を、数日前に到着したこのブルガルで知りました」
「・・・・・・ですが希望は残されていました。娘は生き延びたというのです。一人で草原に残り暮らしていると・・・・・・」
ケントはそこで言葉を切らし、改めてリンに向き直した。
「私は・・・・・・、すぐに分かりました。あなたこそ、リンディス様だと」
「・・・・・・どうしてそう思うの?」
「・・・・・・あなたは、亡き母上、マデリン様によく似ておられる」
「!母さんを知っていたの?」
「直接、お目にかかったことはありませんが、キアラン城で絵姿を何度も拝見しました。」
「部族での私の呼び名は『リン』・・・・・・。でも・・・、父さんも母さんも家族三人の時は、いつも私の事を『リンディス』って呼んでいたわ。なんだか、ヘンな感じ。もう一人ぼっちだと思っていたのに、おじぃちゃんが・・・・・・いるんだ。『リンディス』・・・って呼ばれること、もうないって思ってた・・・・・・」
そう言うと、リンは眼を伏せた。
「・・・・・・」
リンディスという名前は、サカでは聞きなれない名前だ。元々サカの民は大抵二文字、長くても三文字の短い名前をつける風習があったので、両親がつけてくれたこの名前を部族の皆はリンと略称して呼んでいた。リンディスという名では両親しか呼ばれないものなので、久しぶりに聞いた本名は、亡き両親を思い起こさせ、感傷を誘った。
母がなぜ十六年もたってから手紙を出したのか、リンには何となく想像できた。
リンが生まれ、成長するにつれ故郷に一人残してきた父が気掛かりになっていたのだろう。唯一の娘である自分が側にいない父はきっと寂しい思いをしているに違いない。子供を育ててから初めて理解できる親の気持ちだ。だからせめて自分の居場所と、孫の存在を知らせたかったのだろう。
ふと、リンはある事を思い出し、眼を見開いた。
「
第一章 運命の足音 5
「それで・・・・・・、リキアの騎士のお二人さん。話を聞かせてもらえるんだったわね?」
二人の騎士は乗っていた馬を降り、リンの前に進むと口を開いた。
「はい。我らは、リキアのキアラン領からある方を訪ねに参りました」
「リキア・・・・・・・。西南の山を越えたところにある国ね?」
サカから出たことのないリンだが、おおよその国の位置は知っていた。
自分の知識を正しかった事を肯定するように、ケントはうなずいた。
「そうです・・・・・・。十六年前に遊牧民の青年と駆け落ちしたマデリン様の使者として」
「・・・・・・マデリン?」
「我らが主人、キアラン侯爵、ハウゼン様のたった一人のご令嬢です。ずっと消息を知れず、侯爵も、もう娘はいないものだとあきらめておられました」
「しかし、今年になって初めてマデリン様からの便りが届いたのです!『サカの草原で、親子三人、幸せに暮らしている』。その事に、侯爵はとても喜ばれ自分には『十五になる孫娘がいる。知らぬ間に、おじぃちゃんになっていたようだ』と、それは、幸せそうな顔で発表なさいました。孫につけられたという名前『リンディス』は、侯爵が、早くに亡くされた奥様方のお名前だったのです。」
「リンディス・・・・・・」
「娘夫婦の思いやりに、頑なだった心も、とかされたのでしょう。なんとか、ひと目なり娘たちに会いたいと願われ、我らがここに来たんですが・・・・・・。マデリン様は、手紙を出した直後、亡くなられていて・・・・・・、その事を、数日前に到着したこのブルガルで知りました」
「・・・・・・ですが希望は残されていました。娘は生き延びたというのです。一人で草原に残り暮らしていると・・・・・・」
ケントはそこで言葉を切らし、改めてリンに向き直した。
「私は・・・・・・、すぐに分かりました。あなたこそ、リンディス様だと」
「・・・・・・どうしてそう思うの?」
「・・・・・・あなたは、亡き母上、マデリン様によく似ておられる」
「!母さんを知っていたの?」
「直接、お目にかかったことはありませんが、キアラン城で絵姿を何度も拝見しました。」
「部族での私の呼び名は『リン』・・・・・・。でも・・・、父さんも母さんも家族三人の時は、いつも私の事を『リンディス』って呼んでいたわ。なんだか、ヘンな感じ。もう一人ぼっちだと思っていたのに、おじぃちゃんが・・・・・・いるんだ。『リンディス』・・・って呼ばれること、もうないって思ってた・・・・・・」
そう言うと、リンは眼を伏せた。
「・・・・・・」
リンディスという名前は、サカでは聞きなれない名前だ。元々サカの民は大抵二文字、長くても三文字の短い名前をつける風習があったので、両親がつけてくれたこの名前を部族の皆はリンと略称して呼んでいた。リンディスという名では両親しか呼ばれないものなので、久しぶりに聞いた本名は、亡き両親を思い起こさせ、感傷を誘った。
母がなぜ十六年もたってから手紙を出したのか、リンには何となく想像できた。
リンが生まれ、成長するにつれ故郷に一人残してきた父が気掛かりになっていたのだろう。唯一の娘である自分が側にいない父はきっと寂しい思いをしているに違いない。子供を育ててから初めて理解できる親の気持ちだ。だからせめて自分の居場所と、孫の存在を知らせたかったのだろう。
ふと、リンはある事を思い出し、眼を見開いた。
「・・・・・・違う!さっきのヤツも、私を『リンディス』って呼んだわ!!」
「!?まさか・・・・・・」
「ラングレン殿の手の者・・・・・・だよな?」
不意にセインからこぼれた名前に、リンは反応した。
「ラングレン?誰?」
「キアラン侯爵の弟君です。マデリン様は、戻らないものと誰もが思っておりましたので、その場合、ラングレン殿が次の侯爵を継ぐはずでした」
「つまり、あなたの大叔父上はあなたに生きておられると困るって事なんです」
「そんな・・・・・・。だって私、爵位になんて興味ないわ!」
祖父が生きていたことは嬉しい。しかし、爵位や財産といったものを継ぐというのは別の話だ。リンはたった一人の身内が気になっていただけで、それ以上のことは考えていない。
そもそも草原で遊牧をして生活するサカの民には権力欲や物欲は乏しい。
というのも広い草原を移動しつつの生活のため、余計な物を取っておくことは出来ず、家畜以外の財産らしい物を蓄えられない。むしろ余分な物を持つこと自体をサカの民は蔑む。
そして何より草原で得られる物は全て、父なる空と母なる大地の恵み。そして死する時、それらは父なる空と母なる大地に還す・・・・・・。そういう共通の考えが、サカの民には存在していた。
そのためリンも爵位など余計な物は必要がないと思ったのである。
「残念ながら・・・・・・、そんなことが通じる相手じゃないんです。これから先も、リンディス様のお命を執拗に狙い続けるでしょうね」
リキアの貴族がそんなサカ独特の考えを知る由もない。セインの言葉にはそれを如実に物語っていた。
「・・・・・・どうすればいいの?」
「我々と共に、キアランへ。このままでは危険です・・・・・・」
ケントの言葉に、リンは素直にうなずいた。
「・・・・・・それしかないわね。わかった、キアランへ行くわ」
一度も見た事のない祖父に会ってみたい。
リンはまだ見ぬ祖父の顔を想像しながら、ケント、セインと共に歩みだした。
表示オプション
横に並べて表示:
変化行の前後のみ表示: