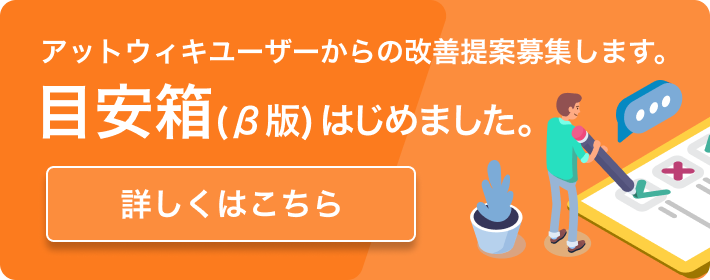小説
かまいたちの夜 1
最終更新:
匿名ユーザー
-
view
心地よい振動は、眠気を誘うものだ。
焦点のさだまらない眼で、彼女が言う。
「あなた・・・・誰?」
・・・・・・寝ぼけてるのか?
焦点のさだまらない眼で、彼女が言う。
「あなた・・・・誰?」
・・・・・・寝ぼけてるのか?
松本の駅を過ぎ、列車が北上するに従って、窓の外の景色は見る間に白銀の世界に変わっていった。
トンネルを抜けると・・・・・なんて劇的な変わり方ではなかったが、ぼく達はまさに雪国へとやってきたのだった。
線路に沿って南北に連なる白馬の山並みは、文字通り白い馬の背を思わせた。雲一つなく晴れ渡った空の下、真っ白な峰は眩しいほどに輝きを放っていた。
「さぁ、そろそろ到着ね」
列車のアナウンスを聞いて真理が言った時、旅が終わってしまうような気がしてぼくはほんの少しがっかりした。しかしもちろん、旅はまだ始まったばかりなのである。
今日の真理は、黒いタートルネックのセーターに、スリムのジーンズ。列車の暖房はむせ返るほどむっとしていたので、もちろん上着は脱いでいる。
くせのない長い黒髪、全体に小作りな顔の中できらきらと目立つ大きな瞳――。やっぱり可愛いよな、今更ながらそう思った。
「何ぼーっとしてるの?さ、早く荷物下ろしてよ」
「ぁ、ごめん」
ぼくは立ち上がり、網棚乗せられた二人のバックを引っ張り下ろした。たかだか二泊三日の旅行だが、スキーともなるとウェアと着替えでバックはえらく大きいものが必要となるものだ。その上スキー一式を担いでいる乗客も大勢いる。そんな苦労をしてまでもやりたいというほど、スキーとは楽しいものなのだろうか。
実際、スキーよりも、真理と一緒にいられるだけで幸せだった。
絶対に面白いから、という真理の言葉を信じついては来たものの、楽しむレベルになれるかどうか、はなはだ不安だった。
駅前の広いロータリーにはスキー場行きのバスやタクシーがいくつか止まっていた。スキー列車が吐き出した乗客達の多くはそちらへ向かったが、真理はぐるりと辺りを見渡し、やがて何かを見つけたのか手を振り始めた。
「叔父さん!」
少し離れたところにいたシルバーグレーのワゴンが動き出し、ぼく達の真ん前で来て止まった。
「やぁ、真理ちゃん。久しぶり」
運転席に座っていた男の人が顔をほころばせて声をかける。
「さぁ、乗って」
一番後ろの席に荷物を放り込むと、ぼく達は真ん中座席に並んで腰掛けた。
「これが私の叔父さんで、小林次郎さん。ペンション『シュプール』のご主人様よ」
「どうも。お世話になります」
ぼくはぺこんと頭を下げた。
「いらっしゃい。君が透君?スキーははじめてなんだって?」
小林さんは車を発信させながらルームミラー越しに笑いかける。
どうやら真理はある程度ぼくの事を彼に話しているようだった。
「ぇぇ、そうなんです」
「真理ちゃんのしごきについていくのは大変かもしれないね。覚悟しておいた方がいいな」
「やだ、叔父さん。しごいたりなんかしないわよ」
ぼくは声を上げて笑ったが、これが小林さんの冗談ではないことがすぐ分かることとなる。
トンネルを抜けると・・・・・なんて劇的な変わり方ではなかったが、ぼく達はまさに雪国へとやってきたのだった。
線路に沿って南北に連なる白馬の山並みは、文字通り白い馬の背を思わせた。雲一つなく晴れ渡った空の下、真っ白な峰は眩しいほどに輝きを放っていた。
「さぁ、そろそろ到着ね」
列車のアナウンスを聞いて真理が言った時、旅が終わってしまうような気がしてぼくはほんの少しがっかりした。しかしもちろん、旅はまだ始まったばかりなのである。
今日の真理は、黒いタートルネックのセーターに、スリムのジーンズ。列車の暖房はむせ返るほどむっとしていたので、もちろん上着は脱いでいる。
くせのない長い黒髪、全体に小作りな顔の中できらきらと目立つ大きな瞳――。やっぱり可愛いよな、今更ながらそう思った。
「何ぼーっとしてるの?さ、早く荷物下ろしてよ」
「ぁ、ごめん」
ぼくは立ち上がり、網棚乗せられた二人のバックを引っ張り下ろした。たかだか二泊三日の旅行だが、スキーともなるとウェアと着替えでバックはえらく大きいものが必要となるものだ。その上スキー一式を担いでいる乗客も大勢いる。そんな苦労をしてまでもやりたいというほど、スキーとは楽しいものなのだろうか。
実際、スキーよりも、真理と一緒にいられるだけで幸せだった。
絶対に面白いから、という真理の言葉を信じついては来たものの、楽しむレベルになれるかどうか、はなはだ不安だった。
駅前の広いロータリーにはスキー場行きのバスやタクシーがいくつか止まっていた。スキー列車が吐き出した乗客達の多くはそちらへ向かったが、真理はぐるりと辺りを見渡し、やがて何かを見つけたのか手を振り始めた。
「叔父さん!」
少し離れたところにいたシルバーグレーのワゴンが動き出し、ぼく達の真ん前で来て止まった。
「やぁ、真理ちゃん。久しぶり」
運転席に座っていた男の人が顔をほころばせて声をかける。
「さぁ、乗って」
一番後ろの席に荷物を放り込むと、ぼく達は真ん中座席に並んで腰掛けた。
「これが私の叔父さんで、小林次郎さん。ペンション『シュプール』のご主人様よ」
「どうも。お世話になります」
ぼくはぺこんと頭を下げた。
「いらっしゃい。君が透君?スキーははじめてなんだって?」
小林さんは車を発信させながらルームミラー越しに笑いかける。
どうやら真理はある程度ぼくの事を彼に話しているようだった。
「ぇぇ、そうなんです」
「真理ちゃんのしごきについていくのは大変かもしれないね。覚悟しておいた方がいいな」
「やだ、叔父さん。しごいたりなんかしないわよ」
ぼくは声を上げて笑ったが、これが小林さんの冗談ではないことがすぐ分かることとなる。