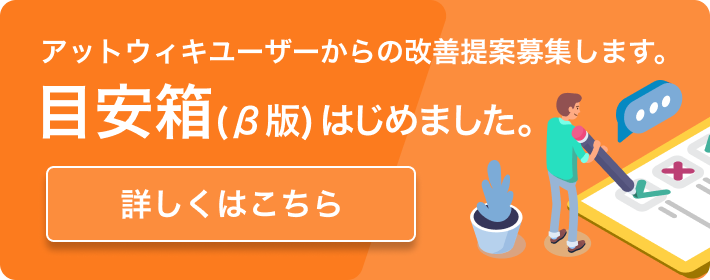小説
かまいたちの夜 3
最終更新:
匿名ユーザー
-
view
『シュプール』にたどり着くと、改めてゆっくりと観察した。
小林夫妻が経営するこの『シュプール』は、外観はログキャビン風で、内装は白を基調にしたおしゃれなペンションだった。
料理のメニューも多国籍というか無国籍というか、とにかく多彩で、その上味も満足いくものばかり。閑古鳥が鳴くどころか、雑誌などにも紹介されて人気も出てきているらしい。暇だから格安で・・・。というのは、小林さんがぼく達に気をつかわせまいとして言ったのだと、昨日到着してから気付いた。
乾燥室にスキー一式を入れると、ぼく達は中へ上がった。車の音でぼく達の帰還がわかったのだろう、小林さんが出迎えてくれ声をかけてくれた。
「お帰り。――彼は、どうだった?」
「まあ、あんなもんでしょ。もうちょっと根性あるかと思ってたんだけど」
「厳しいね。――透君、明日は体が動かないかもしれないよ。筋肉痛の薬貸して上げるから、寝る前に塗っておくといい」
「はい、ありがとうございます」
ぼくと真理の部屋は残念なことに、というか当然、別々にとってある。ユニットバスがついているので、軽く汗を流した後、ベッドに倒れ込んだ。
少しうとうとしたかと思うと、すぐにノックの音が響いた。
「もう夕食よ」
真理だ。ぼくをわざわざ起こしに来てくれたのだろう、まだ意識が朦朧とする僕はのそのそとベッドから起きあがり、真理と食堂へと向かった。
食堂のテーブルにはすでに、ナイフやフォークがセットされていた。
女の子三人組やさっき着いた夫婦も、もう先に椅子に座っていた。
真理がさっさと座ったテーブルに、ぼくも腰掛ける。テーブルの真ん中にはクリスマスツリーを模したキャンドルが立っている。その揺らめく小さな炎が、窓の外を見つめる真理の横顔を、ほの赤く照らしている。
「きれいだ」・・・・思わずそう言ってしまいそうになったが、なんとか押し止めることが出来た。
「どうしたの?そんなにぽかんとしちゃって。そんなにお腹すいた?」
・・・やれやれ。
小林さんの奥さん、今日子さんと、バイトのみどりさんの二人が、料理を各テーブルに運ぶ。泊り客は、ぼく達、三人娘、そして遅れてきた夫婦・・・。だけかと思っていたのだが、もう一人、こんなペンションに似つかなわしくない客がいた。
食堂の隅、壁に溶け込むようにして座っている、コートの男。食事中だというのに上着も帽子も脱がず、あまつさえ黒いサングラスまでかけている。スキー客にはもちろん、仕事で来ている営業マンにすら見えない。
・・・ヤクザ。それがぼくの第一印象だった。が、よく考えたら、ヤクザが一人でペンションに来るとも思えない。おとなしくスープをすすってるいるその様子を見ていると、みかけと違って気のいい人なのかもしれないとも思えてくる。
いずれにしてもぼく達の前に料理が運ばれてくると、そんなことはすっかりどうでもよくなってしまった。
「おいしい!」
真理はスープを一口含むと、声をもらした。小さな角切り野菜のたくさん入った、ミネストローネとかいうイタリア料理だ。熱々のそのスープはほんとうにおいしくて体の奥から暖まるようだった。
その後に出てきた料理も、どれも味、量、共に満足のいくものばかりで、ペンションとしてではなく、レストランとしてやって行けそうだと、改めて思った。
「これって叔母さんが作ってるの?」
食後のコーヒーの時、ぼくは真理にたずねた。
「ううん。叔母さんは手伝ってるだけよ、料理を作ってるのは叔父さんの方。小さい頃から料理人になりたかったんですって。」
「ふうん」
「それにね実は叔母さん、料理がとても下手なのよ・・・」
「・・・・でも大変なんだろうな」
僕は感心した。
「そうでしょうね。でもたまたまお祖父さんがこのあたりの山をいくつも持っててね。土地だけは初めからあったから、そういう面ではそんなに苦労はなかったみたいよ」
そんな会話をしているうちに食事を終えた人々が、三々五々、食堂を出て行く。ぼくのデジタル時計は19:55を示している。
「さてと。私たちもそろそろ行きましょ」
そう言うと真理は立ち上がった。
「うん」
ぼくもそれにつられて重い腰を上げた。
小林夫妻が経営するこの『シュプール』は、外観はログキャビン風で、内装は白を基調にしたおしゃれなペンションだった。
料理のメニューも多国籍というか無国籍というか、とにかく多彩で、その上味も満足いくものばかり。閑古鳥が鳴くどころか、雑誌などにも紹介されて人気も出てきているらしい。暇だから格安で・・・。というのは、小林さんがぼく達に気をつかわせまいとして言ったのだと、昨日到着してから気付いた。
乾燥室にスキー一式を入れると、ぼく達は中へ上がった。車の音でぼく達の帰還がわかったのだろう、小林さんが出迎えてくれ声をかけてくれた。
「お帰り。――彼は、どうだった?」
「まあ、あんなもんでしょ。もうちょっと根性あるかと思ってたんだけど」
「厳しいね。――透君、明日は体が動かないかもしれないよ。筋肉痛の薬貸して上げるから、寝る前に塗っておくといい」
「はい、ありがとうございます」
ぼくと真理の部屋は残念なことに、というか当然、別々にとってある。ユニットバスがついているので、軽く汗を流した後、ベッドに倒れ込んだ。
少しうとうとしたかと思うと、すぐにノックの音が響いた。
「もう夕食よ」
真理だ。ぼくをわざわざ起こしに来てくれたのだろう、まだ意識が朦朧とする僕はのそのそとベッドから起きあがり、真理と食堂へと向かった。
食堂のテーブルにはすでに、ナイフやフォークがセットされていた。
女の子三人組やさっき着いた夫婦も、もう先に椅子に座っていた。
真理がさっさと座ったテーブルに、ぼくも腰掛ける。テーブルの真ん中にはクリスマスツリーを模したキャンドルが立っている。その揺らめく小さな炎が、窓の外を見つめる真理の横顔を、ほの赤く照らしている。
「きれいだ」・・・・思わずそう言ってしまいそうになったが、なんとか押し止めることが出来た。
「どうしたの?そんなにぽかんとしちゃって。そんなにお腹すいた?」
・・・やれやれ。
小林さんの奥さん、今日子さんと、バイトのみどりさんの二人が、料理を各テーブルに運ぶ。泊り客は、ぼく達、三人娘、そして遅れてきた夫婦・・・。だけかと思っていたのだが、もう一人、こんなペンションに似つかなわしくない客がいた。
食堂の隅、壁に溶け込むようにして座っている、コートの男。食事中だというのに上着も帽子も脱がず、あまつさえ黒いサングラスまでかけている。スキー客にはもちろん、仕事で来ている営業マンにすら見えない。
・・・ヤクザ。それがぼくの第一印象だった。が、よく考えたら、ヤクザが一人でペンションに来るとも思えない。おとなしくスープをすすってるいるその様子を見ていると、みかけと違って気のいい人なのかもしれないとも思えてくる。
いずれにしてもぼく達の前に料理が運ばれてくると、そんなことはすっかりどうでもよくなってしまった。
「おいしい!」
真理はスープを一口含むと、声をもらした。小さな角切り野菜のたくさん入った、ミネストローネとかいうイタリア料理だ。熱々のそのスープはほんとうにおいしくて体の奥から暖まるようだった。
その後に出てきた料理も、どれも味、量、共に満足のいくものばかりで、ペンションとしてではなく、レストランとしてやって行けそうだと、改めて思った。
「これって叔母さんが作ってるの?」
食後のコーヒーの時、ぼくは真理にたずねた。
「ううん。叔母さんは手伝ってるだけよ、料理を作ってるのは叔父さんの方。小さい頃から料理人になりたかったんですって。」
「ふうん」
「それにね実は叔母さん、料理がとても下手なのよ・・・」
「・・・・でも大変なんだろうな」
僕は感心した。
「そうでしょうね。でもたまたまお祖父さんがこのあたりの山をいくつも持っててね。土地だけは初めからあったから、そういう面ではそんなに苦労はなかったみたいよ」
そんな会話をしているうちに食事を終えた人々が、三々五々、食堂を出て行く。ぼくのデジタル時計は19:55を示している。
「さてと。私たちもそろそろ行きましょ」
そう言うと真理は立ち上がった。
「うん」
ぼくもそれにつられて重い腰を上げた。