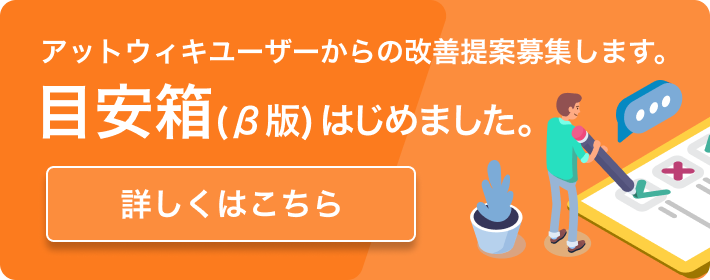axum @Wiki
Kenji ENO
最終更新:
匿名ユーザー
(タイトル)
WARP・飯野賢治のゲームとは何だったのか?
(サブタイトル)
真っ黒なゲーム画面に映るもの
(つかみ)
90年代後半、ソフト開発会社WARPとゲームクリエイター・飯野賢治(元・WARP代表)がゲーム業界に登場する。飯野氏の過激な発言や行動、作品の独特なゲーム性はゲーム界を震撼させたが、取り上げられたのはそれらゲームの「側面」ばかりであったように思われる。しかし、WARP・飯野賢治のゲームは当時の硬直したゲーム界に確かに一石を投じたし、それは今もなお有効ではないだろうか。
その「一石」とは何だったのか?WARP・飯野賢治が手がけた三本のゲーム作品を振り返り、論じる。
(本文)
2004年。アテネオリンピックに湧いたこの年は、同時にゲーム業界にとってある節目になる。
話は今から10年前に遡る。1994年、年末。ソニー・コンピュータエンタテインメントからプレイステーションが、セガ・エンタープライゼス(現セガ)からセガサターンが発売された。俗にいう「ゲーム次世代機」時代への突入である。セガサターンと同時に発売された「バーチャファイター」(セガ、1994年)ではポリゴンのキャラクターを自由に動かすことができ、「次世代機」はゲームのグラフィック性能や音の質が格段に向上したことを示した。
これらの次世代機が登場した1994年に、飯野賢治の率いるソフト開発会社「WARP」も誕生している。WARPは、飯野賢治自らがプロデュース・脚本・音楽・監督・作曲を行った「Dの食卓」を1995年に発売する。「Dの食卓」は3DリアルタイムCGで描かれた主人公・ローラが城の中を散策するアドベンチャーゲームで、3Dで描かれた世界が当時、新鮮であった。主人公・ローラの表情は多彩で、道具のひとつひとつも細部まで描かれている。グラフィック性能の向上と3DリアルタイムCG技術により、この世界観を生み出すことができたといえる。そしてその「映画的な世界」をプレイヤーが探索するという点で「インタラクティヴ・シネマ」という名に恥じないゲームであるといえるだろう。それまでのゲームがなしえなかった内容であり、「Dの食卓」は1995年にマルチメディアグランプリ(通産大臣賞)を受賞する。ゲーム業界では初の受賞であるが、これは画像の性能の向上、つまり3Dグラフィックによるところが大きいだろう。その点で、「Dの食卓」は次世代機へ移り変わった時代の中で重要な作品に位置付けられる。
発売前から大きな話題を呼んだ、WARPのセガサターン二作目「エネミー・ゼロ」(1996年)は「インタラクティヴ・ムービー」とジャンル分けされるように、前作Dの食卓と同じ系譜上の作品と捉えることができる。エネミー・ゼロではストーリーが大幅に増加、グラフィックがさらに進化、音楽には映画「ピアノ・レッスン」の音楽を手がけた音楽家、マイケル・ナイマンを起用するなど、ゲームがさらに映画に近づいたようであった。
このように、WARPは高い技術と質で業界を牽引した。しかし、<何か>が足りないのもWARPのゲームの特徴である。その<何か>はゲームごとに異なるが、その足りないものがWARPのゲームの主題に大きく結びついているように思う。
例えば「Dの食卓」では主人公ローラには過去の「記憶」が欠けている。ゲームを進めるにしたがって、その記憶のかけらが少しずつ表れ、ゲームで起こる事件の全貌に迫ってゆく。(段落つめる)「エネミー・ゼロ」で欠けていたのは「敵」だった。正確にいえば、敵はいるがその姿が見えないのである。見えない敵を「音」を頼りに倒しながら進めていくゲームで、敵が見えないからこそプレイヤーに想像力を働かせ、緊張感を生むことに成功している。また、エネミー・ゼロでは敵が見えないにもかかわらず、エネミーのデザインに造形家の韮澤靖を起用している。その姿が「見えないから」という理由で敵の造形をなおざりにしていない。そしてこれは必要な<不在>であったといえるだろう。姿が見えないエネミーは、ガンで倒されたときやゲーム内のムービーで一瞬だけ、その姿の一部を目にすることができる。一瞬だけ一部分が映るエネミーの姿が美しいから、そして不気味だからこそプレイヤーにその「見えない」姿を想像させることを可能にするのである。敵の造形ひとつをとっても、プレイヤーの想像力を喚起するような作者の意図が見て取れる。
この「想像」というキーワードはWARPのゲームにおいて重要である。この「想像」をキーワードとした革新的なゲームが1997年に登場する。それがWARPのセガサターン三作目、「リアルサウンド~風のリグレット~」(1997年)である。このゲームで話題になったのは、ゲーム画面が無いということだ。皆がずっと追い求めていたはずのグラフィックを、WARPは消したのである。
ところで、このゲームについて語る前に、次世代機が世に出てからの当時のゲーム業界の状況を振り返ってみたい。リアルサウンドが発売されたのは1997年7月。プレイステーションとセガサターンの次世代機発売から二年以上経ち、ゲームクリエイターが新たなハードをうまく扱えるようになり、グラフィック性能に驚くべき進歩が訪れたといわれている。もはや「バーチャファイター」のグラフィックも見劣りするようになった。美しいCGムービーが「映画のよう」と絶賛され、400万枚売り上げたともいわれる「ファイナルファンタジー7」(以下、FF7)が発売されたのもこの1997年である。FF7が多くの人々の興味をひいたのは「ファイナルファンタジー」というブランドやストーリーの内容はもちろんだが、当時最高峰の美しいグラフィックにあったことに異論は無いはずだ。このように、当時のゲームは今までのゲームがなしえなかった「グラフィック」「映像」「音楽」のクオリティの高さから、すなわち「外見」で評価されていたように思われる。
そして現在、ゲームのグラフィックはさらに進化を遂げ、ゲーム内の世界を見た目には描ききることに成功したといってもいいだろう。しかし、グラフィック性能の向上とは裏腹にゲーム離れという状況が訪れているのも確かだ。その理由について、ゲーム研究者の桝山寛は「技術的な進歩が、一般的に必要とされる以上の飽和点に達してしまった」(『テレビゲーム文化論』講談社現代新書、2001年)からだという。そして発売されるゲームのラインナップは手堅いジャンルや続編に偏っている。
「リアルサウンド」はこのようなゲーム業界の状況を見据えたようなゲームだったように思うのである。リアルサウンドは画面の無いことただ一点のみが注目されたが、この作品は人の想像力を主眼に置いた作品であった。WARP・飯野賢治はなぜ、このような「画面の無い」ゲームをつくったのだろうか。
前二作、「Dの食卓」、「エネミー・ゼロ」では主観視点で進められる展開に加え、次世代機により向上したグラフィックの性能を最大限に引き出すことで、あたかもそこにプレイヤーが参加しているような作品になった。その意味で、「インタラクティブなメディア」としてのゲームをつくるのに、美しいグラフィックは必要だったのである。しかし、ゲーム業界は「ただ美しい」グラフィックを自己目的的に生産し、周囲もそれを称賛した。時代の趨勢といえばそれまでだが、その状況へのアンチテーゼとして、画面を無くすことで人の想像力を喚起する「リアルサウンド」をつくったのではないだろうか。
詩人の清岡卓行は、ミロのヴィーナスが魅惑的なのは「腕を失った」からであるという。「ほかならぬその欠落によって、逆に、可能なあらゆる手への夢を奏でるのである」―ヴィーナスが腕を失ったからこそ、見る人にその無い腕の姿を想像させるのである。この言葉はそのまま、「リアルサウンド」に当てはまるように思われる。音だけで進むストーリーはプレイヤーそれぞれに異なる風景や場面―台風の空や、海辺の町など―を描かせる。
ゲームには様々な可能性があるはずだ。そして、様々な「問題作」を生み出したWARP・飯野賢治が、その可能性を具体的な形で表した最たるものが「リアルサウンド」であったように思う。しかし、「リアルサウンド」は期待されたほどの売り上げを果たさなかった。「ゲーム」としての評価もパッとしなかった。ゲームがゲームの世界だけに閉じてしまった、それまでの評価軸の中ではそれはやむを得ないのかもしれない。しかし、「リアルサウンド」は人の想像力に働きかけるが、インタラクティブを指向した点でラジオドラマとも小説とも異なる。ゲームの枠にとどまらない、いや、ゲームの可能性を広げる作品であったように思うのである。そして当時、その可能性をうまく広げることができたならば、現在のゲーム業界のある臨界を乗り越えることができたのではないかとさえ考えさせられるのである。
真っ黒なゲーム画面は、今もなお我々に語りかけている。<不在>は実に雄弁なのである。
WARP/飯野賢治のゲームと著作
Dの食卓(1995年)
ジャンル:アドベンチャー
ロサンゼルスのダウンタウンの病院で大量殺人事件が発生する。犯人は病院の院長・ハリス。娘ローラが病院に駆けつけ、変貌した父の謎、そして自らの謎に迫ってゆく。2時間に制限されたゲーム時間がプレイに緊張感を生み出す。後半になって難しくなる謎解き。ストーリーが進むに従い明らかになってくる過去…そして「D」とは?「インタラクティヴ・シネマ」として世に衝撃を与えた作品。3DOで発売され、その後セガサターンとプレイステーションに移植された。×××な内容で、当時よく訴えられなかったなぁと思う。
エネミー・ゼロ(1996年)
ジャンル:インタラクティヴ・ムービー
地球に帰還中の宇宙船「ヴィークル・ジ・アキ」に突如、衝撃がはしる。コールドスリープから目覚めたクルーたちを襲ったのは「姿の見えない」敵だった。この見えない敵と「音」を頼りに戦うアクションシーンの恐怖感といったらもう。難しいと非難の声もあがったが、現在インターネットなどで得られる攻略を見ながらでも最後までプレイすることをお勧めする(ストーリーやセリフは一見の価値有り!)。ちなみに本作品は当初プレイステーションで発売予定だったが急遽セガサターンで発売されることになり、波紋を投じた。これは「E0事件」として記憶されている。
リアルサウンド~風のリグレット~(1997年)
ジャンル:インタラクティヴ・サウンド・ドラマ
「画面の無い」ゲーム。青春ラブストーリーで、音だけで進められるストーリーの脚本は「東京ラブストーリー」の脚本を手がけた坂元裕二。テーマは「初恋」。プレイするうちに初恋を思い出してしまうはず。途中で主人公の台詞を選んでいき、その台詞によりエンディングが変化する。恐怖を目指した「リアルサウンド」の続編「霧のオルゴール」が発表されたが発売には至っていない。残念!ところで、プレイ中はみんなどこを見ているのだろうか?(アイマスクをつけてプレイした筆者)
ゲーム Super 27 years life(講談社、1997年)
飯野賢治氏の27歳までの自伝。幼稚園の話から1997年までのジェットコースターのような人生が語られる。19歳での会社設立、エネミー・ゼロのセガサターンへの転向などゲーム業界をかき回す飯野氏の行動ひとつひとつが読者に語りかけるように表現され、グサグサと心身に突き刺さる。飯野氏の行動力に読者は動かされるはず。あっという間に読め、元気が出る本。飯野賢治自身のゲームとともに、硬直したゲーム業界に一石を投じた一冊。