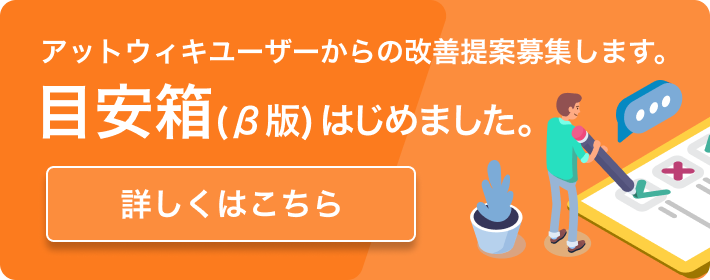同年代の子供たちと比べて、彼女は病弱であり、気弱であった。
何をやるにも行動の遅かった彼女は、からかいの標的だった。
大人であれば「その程度の事」と笑って済ませられる事も、子供にとっては大問題だ。
いじめ、とまでは行かなかったまでも、彼女は同じ子供たちに置いて行かれるのが常であり、劣等感を感じざるを得なかった。
私は生まれつき体が弱いから。
私は女に生まれてしまったから。
私は他の人より、劣っているから。
誰もが人生の中で数回は感じる強烈な劣等感は、彼女の場合、一人の男の子によって取り払われた。
女の人だって、凄い人は居る。
それに凄いっていう基準は、案外適当。
全てが平均という人は、むこせいな面白くない人だよ。
ちょっと大人びて難しい言葉を使ったその男の子は、彼女に色々な話を聞かせた。
庭を飛ぶ蝶に関する知識、英雄の物語、社会の構造と制度、王子と王女の悲恋の話……
彼が話す英雄の物語に、女の子は胸を躍らせた。
彼が物語る悲劇に、女の子は涙を流した。
彼が説明する歴史に、女の子は感心し納得した。
今となっては、名前も顔も思い出せない男の子は、今でも彼女の記憶の中に生きている。
現、聖冠騎士団団長、ナーディア・フォン・クレインベルクの記憶の中に。
「それがお嬢様の初恋の相手にして、理想の殿方なのでございますな。
いやはや、なんとも乙女ですなぁ」
感心20%、からかい80%をいつものにこやかな笑顔に隠しながら、ナーディアの世話係の老婆は笑う。
「……自分でも乙女ちっくだと思う。悪かったわね」
少しふてくされながら、ナーディアは口をとがらせる。
「悪いとは申しておりませんよ。
ですが、理想だけを追い求めていては、目の前の好機を逃すかもしれません」
少女のプラチナブロンドの髪を梳きながら、老婆は尖った口を直させる。
「それがこの退屈な舞踏会だと言うの?
家柄の自慢と社交辞令のオンパレードにはもう飽き飽き」
「少なくとも、聖冠騎士団団長として駆け回るよりは良縁に恵まれる率は高いかと」
幼い頃からの世話係である老婆に、口で勝った事の無いナーディアは、むぅと口をつむぐ。
「娘の幸せを願わない親はおりません。
できるだけ早く騎士団団長から、良妻になって貰いたいのが親心。
顔に傷でも付かないかと心配なのですよ、お察し下さいませ」
老婆はてきぱきと、少女にドレスを着せる。
均整の取れた瑞々しい少女の肢体に、整った顔立ち。
名門貴族クレインベルク家の歴史の中でも、これほどの令嬢はいないだろうとさえ思わせる。
「顔の善し悪しで判断するような上辺だけの男は、願い下げ」
「もちろんでございます。ですが、性格はなかなか見えにくいもの。
そして性格が同じレベルの女性が二人いれば、次には外見が判断材料になるものでございますよ」
またもや、むぅ、とうなる少女に手鏡を見せる。
「お嬢様は少し落ち着いて、ただ微笑んでいれば良いのです。
そして、何人もの殿方とお話し、こちらで性格を判断し選んで差し上げるのです」
鏡の中の、口数を減らせ、と言われた令嬢はそんな腹黒な…と口の中だけで呟き、実際には違う言葉を口にした。
「……ばあやの髪と腹の中は、正反対な色で染まっているのね」
今ではすっかり白くなった頭髪の老婆は、澄ました顔で答える。
「髪の輝きが落ちた分、心に輝きが増しております。
心が目に見えにくいもので、幸いでございました。
このばあやの心が目に見えるものであれば、太陽のように眩しく誰も見る事ができませんから」
二人は、けらけらと笑い合う。
「この真っ暗な貴族社会、ばあやの太陽の光があれば心強いのだけれど」
「温室で太陽の光ばかり浴びていては、花は育ちません。
お嬢様ならば出来ると信じておりますよ」
「都合の良い時だけ、そう言うのだから」
苦笑にやや近い笑顔ではあったが、当初の陰鬱な空気はだいぶ和んだように感じられる。
これが年の功というものだろう、とナーディアは思う。
そんな人生の大先輩は、まるで悪気など欠片もないような笑顔で言うのだ。
「そうです。その笑顔が殿方を釣る良い笑顔なのです。
それと言葉遣いも、この部屋を出たらお改め下さいませ」
このアスガルド半島の主要組織が『法王庁』であるのは間違いない。
だが、旧時代からの特権階級『貴族』たちは未だに半島に存在する。
教典を理由に平等を謳ったところで、法王庁の人間は『侵略者』でしかない。
侵略者に支配されるよりは、元々存在していた『貴族(支配者)』により統治させた方が住民感情の抵抗が少ない。
また半島全てを掌握できるほど、法王庁の人数が多くなかった事もある。
結果、大量の布施が免罪符となり、『貴族』という存在は残り続けている。
「その貴族の力を使わなくちゃ、ままならない……
今の僕はそんな存在でしかない」
自分に言い聞かせるように、キルシェはひとりごちた。
いつもは好奇心の塊、常に前向きと言った様子の彼だが、今は珍しく気が向かない様子である。
彼を知る友人が見れば、何か悪いものでも食ったのか、と心配して声をかけかねない。
そのキルシェの憂鬱の原因は、親から出された交換条件である。
彼の要望は、自身の進学の為の身元保証、大柄な友人の刑期の減少、勝ち気な姉妹への法王庁の研究結果の優先開示、親戚の騎士団入団への口添え、だ。
それに対し両親が出した条件が、有力貴族と結婚を前提とした付き合いをする事。
さしあたっては今日行われるパーティーに出席する、というものだ。
学費や家賃は、彼個人のバイトで(なんとか)まかなえる。
だが、権力的働きかけは、キルシェ一人の力ではどうしようもない。
金や権力が全てだとは思ってはいないが、それの有用性を感情だけで否定するほど子供では無い。
ゆえにキルシェは両親の条件を?み、彼用にオーダーメイドされた礼服を身につけている。
体にはぴったりと合っているはずなのに、それは普段の服装よりも窮屈に感じる。
「……権力に近づきたくない、なんてのは贅沢なのかな」
そう呟くとキルシェは、アスガルド半島有数の貴族クインヒア家のキルシェ・ヴァン・クインヒアは、静かにドアを開いた。